![]()
![]()
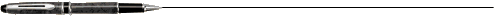
杉田俊明
![]() 2017年版『経営学研究のしおり』掲載論文の全文(計23ページ) (p)
2017年版『経営学研究のしおり』掲載論文の全文(計23ページ) (p)
(下記は概略)
| 第Ⅰ部 なぜ アジア なのか 1、 ミクロの事例からみる日本企業の活動と課題 ― ケースで学ぶアジア(企業)経営論 1-1 話題新興企業のケース 1-2 身近にある流通・サービス企業のケース 2、マクロの統計からみる日本企業の活動と課題 注:前掲データは公的統計を集計・分析のうえ、引用しているものである。 詳細は杉田俊明担当のNHK語学講座テキスト「即戦力のビジネス中国語」のうち、 「杉田教授のビジネススクール」(2011年度版、2012年度版)コラム・シリーズの内容を 参照されたい。但し、最新のデータについては講義中において追記する。 第Ⅱ部 アジア(企業)経営論は何か ― 何を、どう学ぶのか 1、アジアビジネスと関連学問研究領域の発展略史 (筆者がかつて所属していた商社のように、100年も前からアジアでビジネスを行い、 日本の貿易史を書き残してきた企業もあるが)一般に日本企業は60年代から、 特に80年代中盤以後にグローバル展開を行い、その一環としてのアジアビジネスへの 取り組みを深めてきたのである。 そんななかで、従来の欧米を中心とした経営の理論や応用研究のアジアでの適用が 切迫の課題として浮び上り、アジアでの経営に必要な情報や知識、また、 その経営に対応できる専門人材に対する要望が高まってきたため、 学術界も関連研究と教育を急ぐようになった。 1997年頃から日本の大学のなかで横浜国立大学経営学部のように従来の国際経営論や 多国籍企業論(各4単位)と平行してアジア企業経営論(以下、アジア経営論、4単位。 当時の担当:杉田俊明)を先駆的に設置する動きがみられ、国際経営関連の研究と教育が より立体的に行えるようになってきた。 1998年、甲南大学経営学部が関西で最も早くこの流れに対応した大学の一つとして 「アジアビジネス」(現・アジア経営論。いずれも杉田俊明担当)を開講し現在に至っている。 2、定義、体系と研究対象 時代の変化と社会の要望にいち早く対応したアジア経営論は他の学問領域と対比して 歴史は相対的に浅いが、アジアでのビジネス、アジアでの経営が注目を浴びている ことと共に、専門領域における研究が進み、学問体系が整備されつつある。 分かりやすく表現するならば、アジア経営論は国際経営論の源流を踏襲しながら アジアの特性を織り込んだアジア経営研究の特化版とも言える。 日本企業を例にした場合、アジアにおける経営は、アジア(本国以外・異文化圏/ 多文化圏)において、ヒト(人材・労働)、モノ(製品・サービス)、カネ(資金)、 情報(技術やノウハウを含む)などの経営資源をセットにして経営を行うことを意味する。 ここでは経営全体の知識が包括的に求められ、本国(母国)での経営に関わる知識が 必要のみではなく、貿易や直接投資対象国・地域の歴史、文化(言語、宗教を含む)、 社会、政治や経済なども含め、広範囲な知識が必要となる。 このように、アジア経営論は、日本的経営やアジア企業の経営のみならず、 華僑・華人系企業のボーダレス経営、欧米多国籍企業のアジアでの経営も学び、 さらに、それぞれの経営所在国・地域の歴史や文化、社会、政治や経済などに ついても広く学ぶものである。 つまり、アジア経営論は、アジアに対する地域研究をベースにした、 経営関連諸学問の統合科目の一つであり、応用経営学の一つである。 やや専門的に言うならば、時事など表面事象を説明する科目ではなく、 アジア経営論はバックグランドにある国際経営の関連理論(例:3-3を参照)を応用し、 事象の本質や、経営の普遍性と特殊性を探究するものであり、 応用経営学の宿命である問題解決を意図したものである。 詳細については「アジア経営論 その枠組みと課題」 (『経営学のしおり』最新版、甲南大学経営学会刊)と、 大学や大学院での当該専門科目の講義内容を参照されたい。 概念図:アジア経営論のイメージ (講義時の各スライドと解説を参照) 3、アジア経営論の詳細内容とその学びについて 3-1地域別 3-2 属性別 3-3 領域別 例:国際貿易論、直接投資論、狭義の経営論、広義の経営論、 特にHymer, Vernon, Porter, Prahalad, Doz, Hamel, Banney, Dunning, Buckley, Casson, Rugman など 理論大家たちの関連理論 3-4 複合応用(学際・地域横断 など) その他 当研究室のホームページ掲載の杉田俊明論著一覧や関連資料を参照。 |
